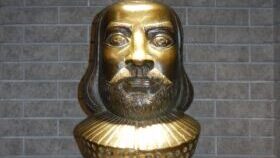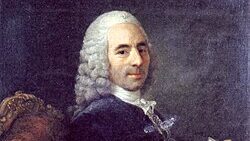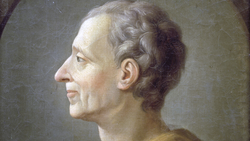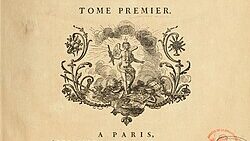簡単で分かりやすい重商主義【定義から各国の特徴まで】
近世ヨーロッパ各国ではイタリア戦争や17世紀の危機や三十年戦争を経験し、主権国家体制が本格的に始まりました。
※イタリア戦争については第一次イタリア戦争に触れた記事とカール5世の人物伝に詳しく載っています。
主権国家とは自分たちの国のことを自分たちで決める国家のこと。その主権国家を維持・成長させるためには
- 官僚制の整備
- 強力な軍事力(常備軍)
が必要不可欠と言われています。
近世よりも前のヨーロッパでは宗教勢力がかなり幅を利かせていたこと、国にもよりますが基本的に諸侯たちが各々力を持っていたことから君主が絶対的な権力者ではなく、いろんなところから横槍が入るような中で政治を執り行っていました。
そんな中で主権国家体制が確立し始めるようになると、官僚制と常備軍の整備が必要になってくるようになりました。そこで、そうした制度や軍を国家財政で賄っていこうとする政策重商主義を様々な国が取りはじめたのです。
ここでは、そんな重商主義についてお話していきます。
重商主義とは
各国はピンチを克服するために経済に介入して自国を富ませる経済政策をとっています。この経済政策は重商主義とよばれます。
※資本主義も経済を重視しますが、民間の産業活動で豊かにしようとする考え方です。
実を言うとこの重商主義政策は絶対王政と切っても切れない関係でした。
絶対王政とは、君主が絶対的な権力を持つ政治体制のことです。
危機を乗り越えるのに国王が集中的な権力を保持していた方が身動きがとりやすくなったのでしょう。時期は異なりますが絶対王政の国が目立ち始めるようになりました。
早い時期から絶対王政が成立したのがスペイン・ポルトガルです。両国はレコンキスタもあって15~16世紀と少し早めに成立しています。他にもイギリスやフランスのブルボン朝なども絶対王政の国として登場しはじめます。
上記に出てきたスペイン・ポルトガルやイギリス、フランスは重商主義を行った国としても知られますので、それぞれ特徴を紹介していきましょう。
上の例では出していませんが、スウェーデンでも絶対王政や重商主義政策が行われていました。イギリスで出された自国の貿易を守るための航海法のような条例も発布されています。
スペイン・ポルトガルにおける重商主義
重商主義の初期形態で、スペイン・ポルトガルが代表的な国です。「金銀含む貴金属を蓄積して国の富にしていこう」というものになります。いわゆる重金主義です。
これはアメリカ大陸の発見と無関係ではなく、ポトシ銀山に代表されるように鉱山の開発や対外征服、略奪といった形で貴金属を手に入れました。
イギリスの重商主義
イギリスの重商主義はテューダー朝時代の海外進出に萌芽が見られます。エリザベス1世の治世下にあたる1600年の東インド会社の設立はその典型です。
そのエリザベス1世には子がおらず、後継者としてスコットランド王ジェームズ6世がジェームズ1世として即位しています。ジェームズ1世は王権神授説を唱え、議会を無視したうえで大商人と結びつきました。
※ジェームズの両親は共にテューダー朝の祖・ヘンリー7世の血を引いている王位継承順の高い人物でした
ちなみにジェームズ1世の本拠地であるスコットランドはカルヴァン派がメインな一方でイングランドは国王を首長とするイギリス国教会。権力を振るいやすい宗派は明確です。

ジェームズ1世も息子チャールズ1世もイギリス国教会の立場に立ち、本拠地でも国教会を強制しようとしてカルヴァン派と対立。
しかも、外から国王となってイギリスの伝統的な政治が分かっておらず、イングランドの方でも敵を作ってしまいます。そうしたカルヴァン派との対立に議会の対立が重なってイギリス革命(1640-1660年)が起こったのです(詳細は別記事)。
1649年にチャールズ1世は処刑され、クロムウェルを中心に共和政をうちたてました。この革命では、カルヴァン派…イギリスでいうところのピューリタンが大きな役割を果たしています。
教義内容からカルヴァン派の信者には商工業者が多数含まれていたんでしたね(『ドイツ以外で誕生した新たな宗派とカトリック教会の反撃』参照)。
そんな背景から革命後の政権では商工業者たちの発言力が高まっていたのです。
イギリスに特徴的な重商主義が始まったのは、そんなイギリス革命以後の17世紀半ば頃から。議会の力が伸びただけでなく、存在感を増していた商工業者達の意向によりイギリスに特徴的な議会的重商主義と呼ばれる重商主義政策がとられました。
彼らは国内の
- 産業活動の自由
- 競合する外国製の商品に対して国内産業を保護
をするよう求めます。
そんな流れの中で1651年には重商主義的な通商政策の一つとして航海法が制定されました。イギリスとその植民地への輸入品はイギリスと原産国の船で輸送することを定めたのです。
航海法の制定は中継貿易で富を得ていたオランダに大ダメージを与えています。そのため、翌年にはオランダと戦争(イギリス=オランダ戦争)に発展しました。
こうした政策をとったイギリスの海外貿易は大きく発展。その状態を維持するため
- 自国製品の販路となる国外市場を拡大させる
- 一部の原料を海外から調達させる
必要が出てきます。
また、17世紀後半には海外物産(特に紅茶+砂糖!)がイギリスの上流階級(貴族・ジェントリ)に、そのうち一般市民に至るまで広範な人々の日常生活に浸透しはじめました。当初は中国から紅茶を仕入れていましたが、供給を安定させるためにインドにも販路を広げていきます。
フランスの重商主義
フランスの重商主義を語るうえで欠かせないのが1660年代に財務総監となったコルベール(1619-1683年)。ルイ14世の治世を支えた重臣の一人です。


コルベールは1664年にフランスでも東インド会社を再建(過去1604年に一度創設しますが、成果が上がらず撤退)させ、64年には西インド会社を作ります。アジア方面(東インド会社が担当)やアフリカ西岸やアメリカ(西インド会社が担当)との貿易振興を目指しました。
※西インド会社は10年後解散しています
さらに、国内では輸出向け商品を製造するための王立マニュファクチュアを創設。ゴブラン織りなどの輸出向け商品をそこで効率的に作り出し、さらに国内の商品移動を活発化させていきました。
こうしたコルベールによる政策はコルベール主義と言われ、国内の商工業育成と貿易振興を推進させました。
なお、コルベール主義は重商主義の中でも「貿易黒字によって金銀を増やす形態」いわゆる貿易差額主義を取り入れています。
海外貿易の販路拡大へ
フランスの重商主義はイギリスの保護貿易のような形とは少し違っていますが、両者ともに自国の商品を売り自国を発展させるためにも海外貿易のための販路拡大が必要になっていきました。海外植民地を強く必要とするようになっていたのです。
イギリス・フランスなどの国々は植民地を巡ってヨーロッパだけでなくアジアやアメリカでも競いはじめました。
17世紀後半から始まったファルツ戦争や18世紀以降のスペイン継承戦争、オーストリア継承戦争、七年戦争。本来なら王位継承争いやその復讐を目的とした戦いだったはずなのですが、どの戦いも植民地戦争に飛び火し、世界中で戦火が広がりました。
なお、今まで経済の優位性を保っていたオランダは激しくなりつつある競争で国家の果たす役割がどんどん強くなる中で、ウィレム3世以降、強力な国家指導者を欠いたため徐々に国際的地位を落としたのでした。
なお、日本における重商主義の先駆者としては田沼意次が知られていますので、良かったらご覧ください。