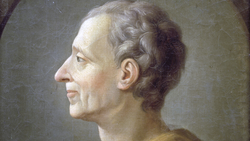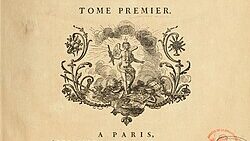科学革命とは?背景・人物・功績を表でわかりやすく
科学革命とは16世紀~17世紀を中心に自然科学が急速に発展した出来事や時期の事を指し、17世紀のヨーロッパは科学革命の時代と呼ばれています。
※19世紀の“科学の制度化”すなわち“科学者”という科学にちなんだ職業が誕生する時期を『第二次科学革命』と称することも。
科学革命以前の世界でも“科学”は全くないわけではありませんでしたが、原始的な試行錯誤による錬金術や観察による推測から理屈に結ぶような“科学”にとどまっていました。
今回は、そうした科学革命がおこった背景やどんな人物が科学に寄与したのかをまとめていきます。
科学革命がおこった背景
ヨーロッパでは、かつて宗教的な伝統や考え方、知識が主流にありました。
それがルネサンスで「宗教が広まる前のローマやギリシア時代の文化を復興しよう」という宗教がすべてという価値観が変化。そこに宗教改革が始まって、完全に神中心の考え方が崩れます。
また、大航海時代に突入し、航海に必要な実用性の高い技術や知識など知見が大きく広がりました(大航海時代初期にカトリックの国々が布教も兼ねて海外進出したので宗教改革も大航海時代と完全に無関係とはいえません)。
実をいうと、大航海時代に広がっていたと知られている『地球平面説』はあくまで俗説で、以前からヨーロッパでは地球が球体であることは周知されていました。
そうした俗説が作られた理由は、17世紀以降にプロテスタントがカトリックを批判するため、なんて言われています。ちなみに(16世紀から)17世紀は『カトリック vs. プロテスタント』をメインとする宗教戦争が頻発した時期です。
17世紀の危機と呼ばれる状況が拍車をかけました。
大航海時代に流入していた大量の資源による急激なインフレ(価格革命)は
- 人口増加(景気好調だからだけでなく、ペストや戦争による人口減少が減ったのも理由)
- 封建社会の崩壊(貨幣経済の浸透と商業の活発化は既得権益層の一部の没落を促した)
- 王権の伸長(②の隙をついて王権が権力を増大させた)
→王権を支えるための軍事力が必要に
などの変化をもたらします。
インフレって必ずしも悪いものではなく、経済が活性化する景気好調期に起こるケースもあるよ!消費者の所得が倍増して企業も投資を活発化させたら豊かな社会になりますね。
しかしながら、価格革命は恩恵を得た者ばかりだけではなく②のように没落する者たちも産み出していました。
そうした状況の中で17世紀に小氷期へと突入。農作物が取れなくなり、安定した社会が崩れ始めると反乱や戦争が相次ぐようになります。飢え・宗教対立・財政難からの中央集権化を目指した王室への不満などが重なったためです。
軍事力が増大されていたのが仇となり、17世紀のヨーロッパで戦争が起こっていなかったのは「わずか4年だけ」なんて言われる状況が出来上がっています。
各国は戦争に追われる中で新たな技術を獲得する必要性が出てきたのです。
当時の科学にまつわる主要人物や組織を紹介
それでは実際にどんな時代に、どんな人たちが新たな“科学”を生み出したのかを見ていきましょう。
16~17世紀、科学革命の中心時期に活躍した人物と功績
| 年 | 人物 | 著作・出来事 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1543 | コペルニクス(波) | 『天球回転論』 | 地動説を理論提案=宇宙像転換の起点 |
| 1609 / 1619 | ケプラー(独) | 『新天文学』 『世界の調和』 | 三法則(楕円軌道の法則・面積速度一定の法則・調和の法則) |
| 1628 | ハーヴェー(英) | 血液循環論 | 血液が心臓を起点に全身を循環することを解剖・実験・数量推定で示した |
| 1610-1632 | ガリレオ・ガリレイ(伊) | 望遠鏡の改良 『天文対話』 | 実験+数学で分析する手法を用いた |
| 1660 / 1666 | ――― | 王立協会(英) パリ科学アカデミー(仏) | 科学者の団体が発足 実験と科学者同士で成果を共有(外部からも検証可能に)=近代科学の制度化 |
| 1661 / 1662 | ボイル(英) | 気体力学 ボイルの法則 | 気体の体積と圧力の反比例(等温過程)を繰り返し実験で確認。真空ポンプ実験(フック協力)で空気の物理的性質を探究。 |
| 1687 | ニュートン(英) | 『プリンキピア』 | 運動三法則+万有引力で統合 |
| 1673 / 1690 | ホイヘンス(蘭) | 振り子時計と等時性 波動説 | 土星環の解釈やタイタンの発見でも知られるが、入試頻出は波動説 |
| 1684 / 1703 | ライプニッツ(独) | 微積分の記法 二進法 | ニュートンとは独立して微積分法を確立し、微分積分の記号を編み出した |
※ケプラーの法則を発見する際、天体の精密な観測データを構築したティコ・ブラーエ(丁)の存在は欠かせません。名前こそ教科書にはありませんが、ケプラーの成果を基に惑星運動の数値比較をしたニュートンなどに間接的な影響を与えたのは確かです。
ケプラーの法則では『円軌道』と『楕円軌道』のひっかけに注意!正しくは『楕円』!!
18世紀以降の科学に寄与した人物と功績
| 年代 | 人物 | 著作・業績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1753 / 1758 | リンネ(典) | 『自然の体系』 『植物の種』 | 生物の学名を属名+種小名の二名法で表す分類法を確立し、近代分類学の基礎を築いた ※『自然の体系』初版は1735年。二名法の命名基準年は、植物=1753年『植物の種』/動物=1758年『自然の体系』第10版 |
| 1796 / 1798 | ジェンナー(英) | 種痘法の確立(1796) 『種痘に関する研究』(1798) | 牛痘を用いて天然痘を予防する種痘法を確立し、近代的予防接種の出発点を築いた |
| 1789 | ラヴォワジエ(仏) | 『化学基本論』 | 燃焼は酸素との化合であることを示し、量的実験で「質量保存の法則」を確立——“近代化学の父”と呼ばれる |
| 1796 / 1799–1825 | ラプラース(仏) | 『世界の体系』(1796:星雲説) 『天体力学』(1799–1825) | ニュートン力学を数学的に体系化し、惑星運動を厳密に解析;カント=ラプラースの星雲説で太陽系の起源を説明 |
| 1769 | ジェームズ・ワット(英) | 蒸気機関の改良(1769年特許) | ニューコメン型を別置復水器などで大幅改良(1769特許)し、蒸気機関を効率化=産業革命を加速させた |
ベーコンとデカルトの方法論の要点整理(帰納法 vs 演繹法)
この時代には、上で紹介した自然科学の大家たちの残した業績とは違った形で科学に貢献した人物たちもいました。「何を知ったか」ではなく「どうやって知るか」科学の進め方を定義したのです。
イギリスのフランシス=ベーコンらの「観察を重んじて一般法則を導く」帰納法を体系化し『経験論』の出発点を示しました。
一方で、フランスのデカルトらによる「数学的な論証法を使って結果を導く」演繹法(えんえきほう)を重視した『合理論』の確立です。
どちらも万能ではなく、帰納法は時間がかかりデータに偏りがあれば誤った結果を導きますし、演繹法も前提を間違えるとやはり誤った結果が導き出されることになります。
こうした違いをまとめたのが下の表です。
| 帰納法(フランシス・ベーコン) | 演繹法(デカルト) | |
|---|---|---|
| 体系化した著作 | 『ノヴム・オルガヌム』(1620) | 『方法序説』(1637) |
| 特徴 | 観察・実験から再現性を重視する方法 | 明らかな原理から論証を進め、数学で自然を説明 |
| 起点 | 観察・実験(事実) | 単純で確実な真理 |
| 手順 | 事実の蓄積 → 一般法則 | 原理 → 論証 → 数学的展開 → 判断 |
| キーフレーズ | 「知は力なり」 | 「われ思う、ゆえにわれあり」 |
| 強み | 実証性・再現性 | 論理の明晰さ・普遍性 |
| 弱み | 拡張に時間がかかる | 現実とのズレのリスク |
『パンセ』で「人間は考える葦である」の言葉を残したパスカル(1623-62)が合理論の流れをくんでいます。また、ニュートンは観測×数学を統合する形で、ガリレオ・ガリレイは実験に数式化を加えるなど帰納法と演繹法を上手く用いています。
他にもそれぞれ帰納法や演繹法の流れをくむ人物たちを紹介していますが、基本は年号・人物・著作・キーワードが優先なので気になる方だけご覧ください。
- 科学に貢献した人たちがどの方法で業績を残したか?ざっくり紹介
-
彼らの多くは帰納法、演繹法を併用して業績を残しているので、どちらかと言えば帰納寄り or 演繹寄り という分け方であるのをご了承ください。
【帰納法寄り】
ケプラー/ボイル/ラヴォワジエ/ハーヴェー/ジェンナー/リンネ【演繹法寄り】
コペルニクス/ホイヘンス/ライプニッツ/ラプラース
こうした方法論の確立は、やがて近代哲学への道を開くようになりました。
やがて18世紀末のドイツに哲学者カントが登場。
彼は『純粋理性批判』(1781/87)で、認識は「感性(空間・時間)で受け取り、悟性(カテゴリー)で法則づける」とし、経験論と合理論を統合する批判哲学を打ち立てドイツ観念論の基礎を築きました。
以降、フィヒテ・シェリング・ヘーゲルへ連なる主要な哲学体系に繋がっていきます。
同時期には経済思想や政治思想・哲学の大家たちも登場することになりますが、別記事で扱う予定です。