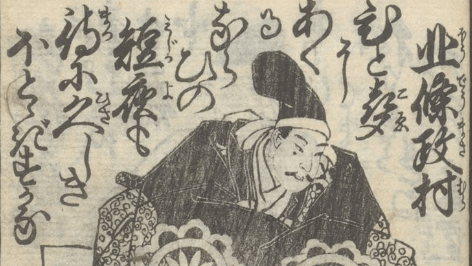鎌倉殿の弟・源義経がどうして最後は頼朝に討たれることになったのか??

『鎌倉殿の13人』でも源頼経と頼朝感動の再開を果たした場面がありましたが、頼朝が鎌倉殿と呼ばれ始めると徐々に確執の片りんが見えるようになりました。
しかし、壇ノ浦の戦いで平家を滅ぼした最大の功労者であることは周知の事実。剣術に優れ、戦術も天才的でした。兄弟間の確執が多少あったとは言え、源平合戦の英雄・義経はどうして源頼朝から謀反者の烙印を押されたのでしょうか??
源義経の誕生と時代背景
1159年、源義朝と妾の【常盤御前】との間に生まれたのが源義経でした。
頼朝とは腹違いの兄弟で、頼朝は3男、義経は9男でした。幼名は【牛若丸】【九朗】と呼ばれていました。
この頃の日本は平治の乱の最中で、頼朝や義経の父・義朝率いる源氏が大敗し平家の棟梁であった平清盛は義朝を処刑します。また、ともに戦った長男・義平と次男・朝長も平治の乱で斬首や討ち死にしています。
3男・頼朝は死罪を免れましたが伊豆へと流刑になりました。
実は、この時に義経も義朝同様に処刑されるはずでしたが、絶世の美女であった母・常盤御前が清盛に見初められたことで【今若】【牛若】【乙若】の3人は助けられ、それぞれが出家させられ寺に引き取られています。
この時、京都の鞍馬寺に預けられた7歳の義経は仏教で太陽と言う意味の【遮那王】と呼ばれ、学問僧として期待され日々勉学に励みました。この時点で、頼朝とはほとんど面識のない状態でした。
平家打倒を決意し藤原秀衡らとの出会い
源義経が15歳になる頃、自分は源義朝の子でその父が平家によって処刑されたことを知ります。『義経記』によると「源氏の血が途絶えることを哀れんだ僧侶が、義経に平家が敵だという事を伝えた」と書かれています。
打倒平家を心に決めた義経は夜ごとに寺を抜け出し武芸に打ち込むようになりました。その行動はやがて平家に知れ渡ることになり、16歳にあると寺を抜け出し忽然と姿を消すのでした。
諸国を転々としていた義経は奥州藤原氏の治める平泉を目指し、3代目・藤原秀衡と出会うと匿われることになりました。
この秀衡の行動には、源氏・平家にとっても義経が意味のある人物であることから『何かあったときにその切り札』として奥州藤原氏有利に働くと考えたと言われています。
こうして義経は秀衡の子供たちと共に養育される事になりました。
そんな中、1180年に兄・頼朝が挙兵します。
頼朝の挙兵を聞きつけた義経はすぐに出陣を決意。わが子のように養育してきた藤原秀衡は義経に頼れる武人を付け、黄瀬川へと送り出します。
そして義経は22歳にして初めて兄・源頼朝と感動的な対面を果たし、ついに宿敵・平家滅亡のために動き出したのです。これは、大河ドラマでもありましたね。
兄・源頼朝との確執

軍略と武勇に優れた源義経は、源平合戦では圧倒的な強さでたちまち有名になりました。しかし、兄である頼朝からは不信感を抱かれるようになっていきます。
その理由と言うのが…
兄の家来は俺の家来だと思っていた
兄・頼朝は、自身が源氏の棟梁となり平氏滅亡と同時に源氏の統一も進めていきました。そのためには、血を分け合った源氏であっても袂を分かつようであれば処罰し、時に強硬な手段で源氏一門を統一しました。
一方で義経は、血のつながった実の兄弟として兄と同じ立場であることを望んでいたと言います。しかし、頼朝からすれば自身は正室の子で正当な血統であり、源氏の棟梁です。そこには兄弟間のなれ合いは良しとせず、主が誰か態度に示せなかった義経に不満を募らせていたのです。
戦では奇襲攻撃ばかりで勝っていた
【三草山の戦い】では、山野全体に火を放ち目をくらまし奇襲をかけ、【一ノ谷の戦い】では、断崖絶壁から奇襲をかけて源氏軍に勝利をもたらしました。
結果オーライではありますが、こうした奇襲攻撃の裏には義経の独断で行ったものが多く、頼朝はこれを良しとしていませんでした。
後白河法皇から官位を勝手にもらっていた
源頼朝は支配圏での序列が乱れないように、承諾もなく源氏一門には朝廷の官職につくことを許していませんでした。そういった決めごとを破り義経は、後白河法皇に言われるがまま官位をもらっていたのです。
さらに梶原景時が「最後の敵は義経なり」と頼朝をそそのかしていたこともあって義経は頼朝の敵とみなされるようになっていきます。
奥州まで落ち延びるが最後は切腹に

頼朝から敵認定された義経は各地を転々としましたが、最後は子供のころにお世話になった藤原秀衡のもとへ身を寄せます。ところが、義経に協力的だった秀衡も病に倒れてしまいます。
臨終の際に秀衡は、これ以上奥州藤原氏がこの土地を治めるのは無理だと説き、義経をトップに藤原兄弟が協力して治めよと言い残しました。しかし、この秀衡の願いは叶う事はなく、藤原泰衡によって反故にされます。
義経と藤原兄弟の不和に漬け込み頼朝は、領土安堵を餌に藤原泰衡に義経討伐の要請しました。討伐に了承した泰衡は3万の軍勢を義経に送り込み追い詰めました。
追い詰められた義経は平泉の持仏堂に入り、妻と娘を刺し自らも切腹し、最期を遂げました。享年30歳でした。
幼き頃に育てられ、人生の最後に頼った場所・平泉は義経とって故郷のような場所だったことでしょう。現在も藤原秀衡の遺体が安置されている中尊寺金色堂や義経と弁慶の木像が奉納されている弁慶堂などに義経が生きた痕跡が残されています。
源義経四天王
源義経に忠義を尽くした側近の事を義経四天王と呼ばれています。
源平盛衰記では屋島の戦いで義経の盾になって命を落とした佐藤継信と継信の弟で義経の影武者佐藤忠信。そして鎌田盛政・光政の4人が居ました。義経と共に戦い、自身の身をもって義経を守り、命を落としていきました。
他に伊勢三郎義盛が義経記に登場する人物で木曽義仲の首を上げるなど源平合戦で数々の戦功をあげた人物も忠義を尽くしました。
また、義経と言ったら武蔵坊弁慶を忘れてはいけません。
伝説の域を超えませんが、義経記や御伽草子に登場し義経の都落ち後にも仕え、最後は義経をかばって数多くの矢を受けて絶命したと言われています。