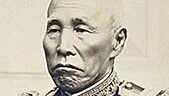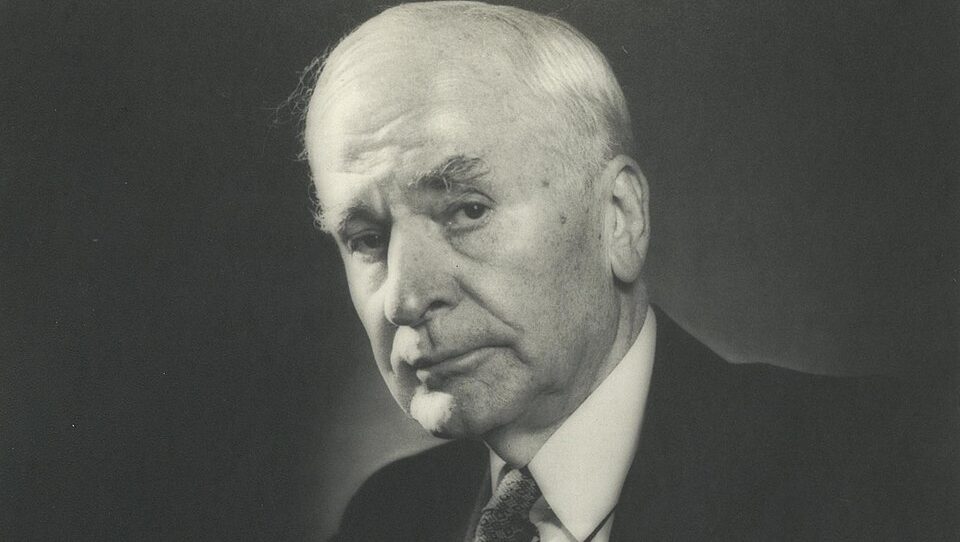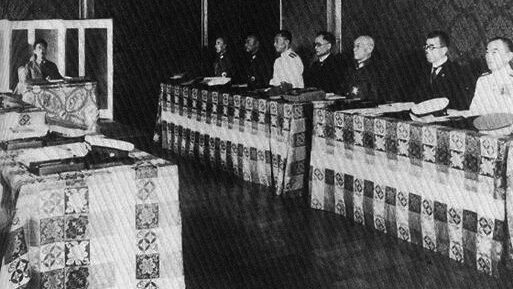日本史視点から見た日露戦争とその背景となる国際関係/ポーツマス条約
前回記事で紹介した、江戸後期の日本に漂着した「はんべんごろう」(ベニョフスキー)の手紙は翻訳の行き違いも手伝って「ロシアが攻めてくる」というイメージを日本社会に残しました。この一件は、誇張半分ではあったものの恐露感情という“北からの不安”を植え付けることになっています。
やがて、三国干渉の屈辱で一気に噴き出し、明治時代の日本はロシア帝国と正面から相まみえることとなりました。
今回は、日露戦争に至る経過と帰結を日本史の視点で整理していこうと思います。
日露戦争が起こるに至った背景
日清戦争(1894-95年)に勝利した日本は、下関条約で台湾・澎湖諸島・遼東半島を獲得したのですが、その直後、三国干渉(露・独・仏)で遼東返還を強いられました。
最大の屈辱となったのは、返還させられたはずの遼東南部(旅順・大連)を今度はロシアが租借(1898)して要塞化・軍港化したこと。並行して、ドイツが膠州湾を、フランスが広州湾を、イギリスが威海衛・九竜半島などを相次ぎ租借。清の沿岸は列強のシマ取り合戦の様相を呈しました。
ちなみに、下の記事は三国干渉が起こった時代前後の日本の政治情勢です。ロシアからの圧力にどう対抗しようか、それには税金が必要だがどのように増税するかなど政党内でバチバチやりあっている様子や選挙権を持つ国民がどの政党を選んだのかなどが書かれています。
極東におけるロシアの南下政策への日本の対応
遼東南部を獲得したロシアはシベリア鉄道・東清鉄道を軸に満州へ兵站を伸ばし、朝鮮半島への干渉も強めはじめました。日本にとって朝鮮は独立を保つべき緩衝地帯であり、ロシアの進出は安全保障の核心に触れてしまいます。
外交では満韓交換(満州の利権はロシアに、朝鮮半島の利権は日本に)の発想も模索されましたが、満州撤兵や朝鮮での自由行動をめぐって折り合いません。そこで日本は1902年、日英同盟を締結。ロシア膨張を望まぬ大英帝国の後ろ盾を得て、外交上の交渉力を高めました。それでも交渉は決裂へと傾いていくことになります。
なお、イギリスがなぜ日本との同盟を結んだかについては『世界史視点から見た日露戦争』の記事で触れています。
恐露感情が噴出した事件/大津事件(1891)
ロシア皇太子ニコライ(のちのニコライ2世)が来日中、大津で巡査津田三蔵に切りつけられて負傷しています。
政府は最大限に謝罪し、大審院長・児島惟謙は法の原則に従い無期徒刑とし、結果として司法権の独立の象徴となりました。事件自体はロシアの対日感情を一時的に硬化させましたが、開戦はあくまで満州・朝鮮をめぐる利害が主因となっています。
日露戦争勃発と満州の陸戦、日本海の決戦(1904–05)
1904年、ついに決裂。日本海軍は旅順港外で露艦隊を奇襲し、陸軍は遼東へ上陸しました。
旅順要塞は粘り強く、第三軍は203高地をめぐって激戦を重ねます。なんとか高地を奪取して観測射撃で港内艦隊を無力化しますが、その代償は重いものでした。
旅順攻囲戦を指揮したのは陸軍大将の乃木希典。
日露戦争では自身の二人の息子を含む多くの犠牲を出して自ら命を絶とうとしますが、明治天皇に反対されていました。そうした日露戦争の出来事も原因となったのでしょう。明治天皇の大葬の日に夫人と共に殉死しています。
満州方面では遼陽・沙河・黒溝台と戦線が北上し、奉天会戦(1905)は近代日本最大級の陸戦となっています。勝ちはしたものの、余力はほぼなく、人的・財政的消耗は深刻なものとなりました。
なお、この旅順攻囲戦の指揮官は陸軍大将の乃木希典。
一方、日露戦争では陸での激しい戦いだけでなく、海でも戦いは行われていました。
1905年には日本海海戦(対馬沖)で東郷平八郎率いる連合艦隊がバルチック艦隊を撃滅しています。「Z旗」とともに示された練度と指揮は世界を驚かせただけでなく、日露戦争の情勢そのものを変えることとなったのです。
しかし、国内では戦費が膨張し、外債にも依存する総力戦の限界が見え始めるようになってきています。
ポーツマス条約の“光と影”
日本国内が戦費で倒れそうになっていた頃。ロシアでも不満が増大。無視できない規模になっていました。
そこで、1905年。米大統領セオドア・ルーズベルトの仲介で講和会議が成立します。
ポーツマス条約で日本は、
・樺太南半の割譲
・遼東半島南部(旅順・大連)の租借権継承(関東州)
・南満州鉄道などの権益
・沿海州・カムチャツカ沿岸の漁業権
を獲得しました。一方で賠償金は一切なし。この条件に不満を持つ民衆は日比谷焼打事件で怒りを可視化しています。
日露戦争は日本の国際的地位を飛躍させ、アジア諸地域の民族運動にも希望を与えましたが、同時に人的・財政の負担、そして大陸権益維持という新たな重荷を背負わせました。戦争での勝利は終点ではなく、次の課題の起点だったのです。
ちなみに...
明治日本は議会・政党・新聞世論の圧力が相対的に大きく、三国干渉後の反露世論、戦時の国債消化、講和条件への不満などが政策判断に影を落としています。他方、ニコライ2世期のロシアは専制色が強く、短期的には皇帝・軍・官僚の判断が優先できたと言えます(ただし敗戦濃厚な空気感や実際の敗戦によって1905年に革命が起こったため長期的な視点に立つと大きな影響を受けたと言えるでしょう)。
対露感情、対日感情はあくまで“一押し”。実際の導火線となっていたのは満州・朝鮮をめぐる構造的対立だったのです。