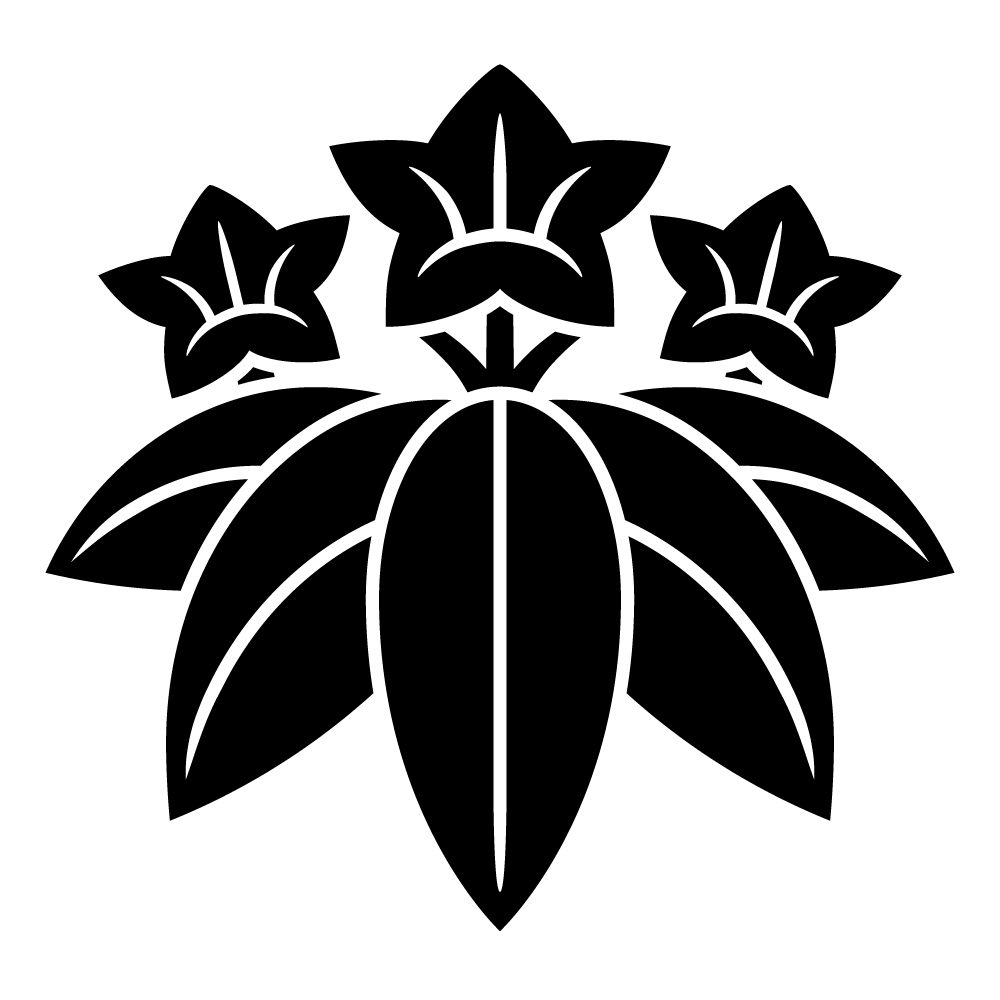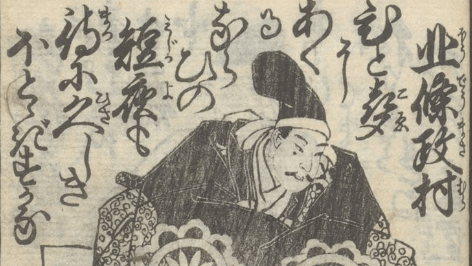日本で初めての朝廷と武家政権の内乱【承久の乱】と北条氏の台頭

承久の乱は、鎌倉幕府が開かれ武家政権が発足しますが、後鳥羽上皇が再び上皇中心の政治を取り戻すべく幕府を打ち取ろうと起こした戦いです。
三代将軍・源実朝が殺されたことを幕府内の混乱と見た後鳥羽上皇は、1221年に執権・北条義時追討の院宣を発布しました。しかし、上皇方に味方するものが少なく、義時は短期間で京都を攻略し上皇軍を破ります。
この戦い後、幕府が朝廷に対して優位に立つことが決定打になり、今まで地頭を置くことのできなかった西国の地にも御家人を派遣し幕府の支配力強化につながりました。
人に不意(1221)うち、承久の乱 ⇒ 1221年 承久の乱
上記の語呂合わせで私は覚えてましたが、皆さんはどうですか??
今回は、そんな鎌倉時代のターニングポイントである承久の乱について書いていきます。
後鳥羽上皇の思惑と勢力拡大
後鳥羽上皇は日々力をつけ政治の実権を握っている鎌倉幕府を何とかして以前のような上皇による親政を考えていました。
そこで、後鳥羽上皇は朝廷の影響力を強めようと三代将軍・源実朝に接近します。
実朝と後鳥羽上皇には和歌の才という共通点などがあり、そうした共通点を通して両者の仲は非常に良好でした。後鳥羽上皇は娘を実朝の妻に差し出すだけでなく、右大臣に任命するなど友好関係を築いていきます。
※源実朝は『金槐和歌集』を作成するほどでした
また、後鳥羽上皇は鎌倉幕府内の権力争いを尻目に領地の拡大と軍事協力を図っていました。分散していた天皇領をまとめて資金を確保し、従来からある北面の武士と西面の武士の集団を設置しました。
当時の各地の荘園は皇室や貴族・寺院に寄進を行っており、後鳥羽上皇の収入源となっていましたが、鎌倉幕府が進める荘園政策により特に東日本の荘園からの寄進が停止。収入が減少していました。
この荘園対策を行っていたのが執権であり得宗家ですから、後鳥羽上皇にしてみれば得宗家に不満を持つのも当然といえそうです。
鎌倉幕府の内紛
この荘園政策を行っていたのは主に実権を握っていた執権・北条氏だったので、後鳥羽上皇は北条氏排除のため鎌倉幕府討伐を考えるようになります。
幕府討伐のチャンスは1219年に訪れました。この時、幕府内では将軍・源実朝が頼家と公暁によって暗殺されたのです。
この幕府内の内乱があれば、御家人同士が争って「朝廷が付け入るスキができるのではないか」と考えた後鳥羽上皇は、幕府討伐を実行に移します。この時の執権が大河ドラマの主人公である北条義時でした。
承久の乱勃発と敗戦

1221年に後鳥羽上皇は、有力御家人に対して義時討伐の院宣を出します。また、朝廷からも義時討伐の官宣旨が出され、承久の乱が始まります。
後鳥羽上皇軍の大将は藤原秀康で、良いタイミングで京都に滞在していた三浦胤義も兵を率いて参戦しました。しかし、想定していた勢力たちが味方に付かず始まってみれば、鎌倉方有利な状況になりました。
さらに、北条政子の有名な演説が絶大な効力を発揮し、鎌倉の御家人たちは結束を強めました。源頼朝の妻・北条政子は、頼朝の恩を説き、一致団結するように呼びかけ、その演説の3日後に北条義時が20万以上の軍勢を京都に差し向けます。
その北条政子が呼びかけた演説と言うのがこちらです。
皆心を一にして奉るべし。これ最期の詞なり。故右大將軍朝敵を征罰し、關東を草創してより以降、官位と云ひ俸祿と云ひ、其の恩既に山嶽よりも高く、溟渤よりも深し。報謝の志これ淺からんや。而るに今逆臣の讒に依り非義の綸旨を下さる。名を惜しむの族は、早く秀康・胤義等を討取り三代將軍の遺蹟を全うすべし。但し院中に參らんと慾する者は、只今申し切るべし。
— 『吾妻鏡』承久三年辛巳五月十九日壬寅条(原文は変体漢文)
原文を書いても何を言ってるのかわからないので、現代語訳にしてみます。
皆、心を一つにして聞くように。
これが私の最後の言葉です。亡き頼朝公は、朝敵である平家を倒し、関東に幕府を開いて以降、朝廷より官位を頂き、俸禄を与えられ、その恩は山よりも高く海よりも深い。報謝の気持ちは決して浅いものではないはずです。
ところが今や逆臣どもの讒言によって、後鳥羽院は幕府追討の非義の綸旨を出されました。名を惜しむ御家人ならば、ただちにこのような偽りの綸旨を出させた藤原秀康、三浦胤義等を討ち取り、亡くなられた三代の将軍の遺業を全うすべきです。
ただし、もし院にお味方したいと言う者がいるのならば、たった今、それを明らかにし、この場を去りなさい
諸説ありますが、北条政子が大勢の御家人の前に演説したとも、幕府の有力御家人が政子の前で上記の声明文を読み上げたともいわれています。
こうした、北条政子の言葉に心を打たれた御家人たちは、宇治川で対峙し後鳥羽上皇軍と激突し、わずか一日で決着が付き上皇の敗北が決定的になりました。
承久の乱の戦後処理と鎌倉幕府の支配力拡大
戦いに敗れた後鳥羽上皇と従った者たちは厳しい処分が言い渡されました。
首謀者である後鳥羽上皇は隠岐の島へ、計画に関わった順徳上皇は佐渡島へ流刑となりました。この時、倒幕に反対していた土御門上皇も自ら申し出て佐渡へ流された他、上皇方の貴族たちも流刑や死罪とされています。
また、上皇方の大将・藤原秀康ら西国の御家人たちの多数が粛清・追放の処分を受けました。
当然、上皇や貴族・御家人たちの西国の荘園は幕府に召し上げられ、それぞれ東国の御家人たちが配置されました。承久の乱以前には影響力を与えることができなかった西国の荘園も、鎌倉幕府の支配下におさめることに成功したのです。
さらに鎌倉幕府は、京都で今後不穏な動きが出ないように六波羅探題と呼ばれる京都の朝廷や西国の御家人の監視する部署を設けました。六波羅探題の長は六波羅守護と呼ばれ、代々北条一門から選ばれています。
この承久の乱によってもたらされたのは
- 武家政権の確立
- 執権・北条氏の権力集中
- 幕府の支配力拡大
この3つ。大切なポイントです!
北条氏による執権政治は承久の乱によって確立し、その後北条義時の子・泰時によって『御成敗式目』と呼ばれる日本初の武家の法律の制定で、その支配をますます強めました。
ちなみ語呂合わせは…
ひとふみに(1232)まとめた御成敗式目
で覚えています。
後鳥羽上皇の最期
朝廷の力を取り戻したいと考えた後鳥羽上皇の願いもむなしく、朝廷の権力は北条一門によって削られることになりました。
一方、隠岐の島に流された後鳥羽上皇は京都に二度と戻らぬまま、島で60年の生涯を閉じ、後鳥羽上皇が島で読んだ和歌が伝えられています。
「我こそは新島もりよ 隠岐の海の 荒き浪かぜ 心して吹け」
【私はこの島の新しい島守です。隠岐の海の荒い波風は、心して吹けよ】という意味で、隠岐の島での後鳥羽上皇の寂しい気持ちが伝わってきます。京都の中心で権力を誇っていた後鳥羽上皇が、隠岐の島でわずかな従者と共に暮らした心持を考えると胸が痛む和歌ですね。
承久の乱でわかる時代の時々で変わる正義
承久の乱では後鳥羽上皇と鎌倉幕府の双方に大義名分がありました。
後鳥羽上皇にとっての大義名分は「日本を統治すべき朝廷がないがしろにされる事が許されることではありません」というものでした。何せ日本で初めての武家政権が誕生した時代ですから、室町・江戸幕府のようにはいきませんよね…
一方で、鎌倉幕府の北条義時・政子からすれば「自身が築いた政権や所領を脅かし、平和を乱す後鳥羽上皇から源家・北条氏に従う御家人たちの安全を守ること」が一大使命です。
結果、承久の乱では鎌倉幕府側が勝利し、後鳥羽上皇が隠岐の島へ流されました。
後の鎌倉幕府の中枢によって編纂された歴史書『吾妻鑑』では、後鳥羽上皇の【反乱】として扱われているに対し、天皇中心の政治に戻った明治・大正時代には鎌倉幕府の北条義時こそが天皇家に背いた逆臣であり、後鳥羽上皇が被害者であるとする考えが主流でした。
私たちが友人や家族・職場等で意見が対立したとき「自分が絶対に正しい」と考えるのではなく、相手の意見に耳を傾け、聞くことができれば無用な争いが避けられるかもしれませんね。