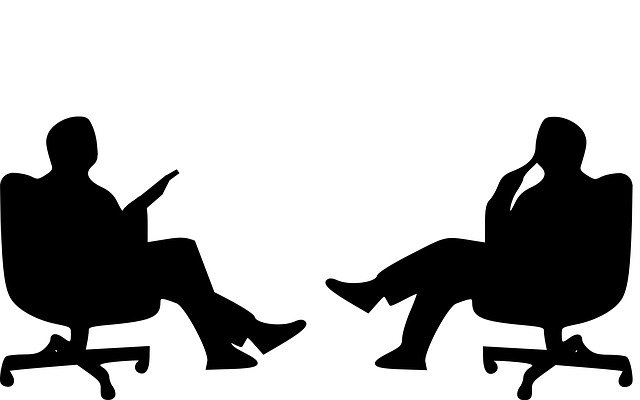2024年発行の新紙幣に描かれる人物3人、どんな人達だったの?

2024年の新紙幣の人物画に渋沢栄一・津田梅子・北里柴三郎が選ばれました。
2023年の4月14日には報道陣に向けて新しいデザインの紙幣が公開されています。
新紙幣発行には、偽造防止など目的に一定期間を経て紙幣や貨幣を新しく発行しています。私はすでに●十年以上生きてきたので、もう3回程新紙幣発行に立ち会っています。
新紙幣には、最先端のホログラム技術が導入され、紙幣を斜めに傾けると肖像が立体的に動いて見える他、透かしは肖像を映し出すだけではなく、紙の厚みを変えて高精度な模様を施しています。
また、文字サイズを大きくして視力が弱くても見やすくしているほか、触って紙幣を識別できるように凹凸が設けられています。
新紙幣に決定した三人の人物は
- 一万円…福沢諭吉 ⇒ 渋沢栄一
- 五千円…樋口一葉 ⇒ 津田梅子
- 千円 …野口英世 ⇒ 北里柴三郎
と変更になります。
デザイン変更に伴い、裏面も変わり1万円は東京駅、五千円は藤の花、千円は葛飾北斎の神奈川沖浪裏となっています。
では、新しい紙幣の顔として選ばれた3人の主な功績など書いて行きましょう。
近代日本経済の父・渋沢栄一は新1万円札

埼玉県深谷市出身の渋沢栄一は、NHKテレビ小説【あさが来た】で、銀行経営指南役として登場し、大河ドラマ【青天をつけ】では、主人公としてその生涯が放送されました。
大河ドラマでは、珍しい文化人という事であまり期待はしていなかったのですが、見てみると意外に面白かったので、再放送で見る機会があれば一気見してみたいなと思っています。
渋沢栄一の記事でも書いていますが、明治~昭和初期にかけて活躍し、彼がかかわった事業は500以上にもおよび、銀行の設立に始まり現在の東京ガスや王子製紙、キリンビールの前身の企業にも携わっています。
新五千円札は津田塾大学創設者・津田梅子
津田塾大学の創設者の津田梅子は、日本の女子教育に尽力し大河ドラマ【八重の桜】では、河北麻友子さんが演じていましたね。
梅子は6歳の時に、岩倉使節団に入り女子留学生として11年間アメリカで暮らしました。一度帰国しましたが、もう一度アメリカへ渡り生物学を学んで津田塾大学の前身・女子英学塾を創設しました。
女性の地位向上が日本の発展になると感じ、生涯情勢の高等教育に力を入れていきました。
日本の近代医学の礎を築いた北里柴三郎は新千円札
ジフテリア・破傷風・抗血清開発などの細菌学分野で功績を挙げたのが北里柴三郎です。
熊本医学校・東京医学校で医学を学び、内務省衛生局に入った後にドイツへ留学。北里柴三郎は、予防医学を重要視しており、破傷風の血清を作り上げたり、香港で蔓延していたペスト調査では自ら現地へ。そして、ペスト菌を発見し細菌学の視点から病気予防に尽力しました。
生涯通じて、いくつもの研究所や病院設立に携わり院長も務めています。
渋沢栄一は書きましたが、残り二人の偉人たちはいずれ記事にしようと思います。
お札の肖像画に選ばれる基準
新紙幣発行のたびに過去の偉人たちが選ばれますが、一体どのような基準で選ばれているのでしょうか?
お札のデザインは、財務省・日本銀行・国立印刷局が協議して、最終決定は財務大臣が決定しているようです。岸田内閣で決定されていたのなら、鈴木俊一大臣で安倍内閣なら麻生太郎氏が決定しいたかもしれませんね。
気になる人選ですが、特に規定はないようですが以下の基準で決めているそうです。
- 国民が世界に誇れる事
- 教科書に載っていて一般的によく知られている事
- 偽造防止のために精密な写真や絵画を手に入れられる事
ちなみに渋沢栄一は、1963年に発効された1000円札にノミネートはあったようですが、髭がなく偽造防止処置が難しいという事で、落選していたようです。この時、明治天皇、伊藤博文、岩倉具視、野口英世、渋沢栄一、内村鑑三、夏目漱石、西周、和気清麻呂の9人が最終候補にあったようですよ。
61年ぶりの復活当選を果たした渋沢栄一の背景には昨今の偽造防止技術が向上した事で、より国民が親しみを持てるような人物が選べるようになったとの事です。
ー追伸ー
少し、宣伝じみて申し訳ありません。
この度、お誘いがあり、yahooクリエイターズプログラムに参加する事になりました。
各種手続きを経て、5月10日より第一作の記事を投稿しております。内容は、日本史が中心で、大河ドラマネタを中心に、その時話題になった人物などを書いて行こうかなと思っています。
また、逃げ上手の若君ネタもやって行こうかなと思っています。
誰にでもわかりやすくサラッと書いているので、興味のあるかたはのぞいてみてください。
Yahoo!JAPAN クリエイターズプログラム 歴ブロのページ