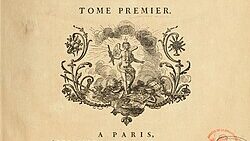『哲学書簡』啓蒙思想家・ヴォルテールってどんな人??【1694-1778年】<人物伝>
ヴォルテール(1694〜1778)は、主にルイ15世の時代に活躍したフランス啓蒙思想の代表的な思想家・作家です。体制批判でバスティーユ監獄送りになった文学者でもあります。
彼が活動した18世紀前半〜後半は絶対王政を築いたルイ14世の後を継いだルイ15世の長い治世(1715〜1774)の時期と重なり、王権の権威が次第に揺らいでいった時代でもありました。
次代のルイ16世の代にフランス革命が起こっていますが、その原因はルイ14世以降の華やかな宮廷生活や度重なる戦争などです。
ルイ15世の代にもポーランド継承戦争やオーストリア継承戦争、七年戦争でさらなる財政悪化を招いています。
このような政治・社会の不安定さの中で、ヴォルテールは王権や教会のあり方を問い直し、「理性」「寛容」「言論の自由」といったテーマを繰り返し訴えていくことになります。
若き日の文筆活動とバスティーユ投獄
ヴォルテールはパリ生まれの作家で、本名はフランソワ=マリ・アルエといいます。
若いころから機知に富んだ詩や戯曲で人気を集め、劇作家・作家として早くから頭角を現しますが、彼の鋭い言葉はたびたび当局と衝突を引き起こしました。
貴族や権力者を皮肉った詩や噂話が問題視され、若いころからバスティーユに投獄される経験をしています。ペンネーム「ヴォルテール」を名乗るようになったのは一度目の投獄の後です。
とくに摂政オルレアン公フィリップ2世や有力貴族ロアン家を怒らせた事件は有名で、風刺や皮肉がどれほど危険な行為だったかが分かります。
オルレアン公フィリップ2世の父親はルイ14世の弟なので、先代国王の甥を怒らせたことを意味します。
しかも!ヴォルテールが捕まったのは1717年でルイ14世が亡くなったのが1715年。ルイ15世はルイ14世の後を継いで5歳で即位したため、摂政が必要な時期でした。宮廷の事実上トップを風刺したことになります。
ロアン家とのトラブルのきっかけは、ロアンの侮辱に対してヴォルテールが言い返したことでした。
ロアンは腹を立てて部下にヴォルテールを殴らせたうえ、決闘で名誉回復を求めようとしたヴォルテールの方をロアン家が手を回して王の命令でバスティーユに送らせています。
経緯を知った世論はヴォルテールに味方していったようです。
ヴォルテールの書いた本格的な処女作は古代ギリシアの三大悲劇詩人のひとりソポクレスが書いた『オイディプス』を再編したものですが、ヴォルテールの『オイディプス(フランス語だとエディップ読み)』には宗教と迷信への攻撃が見え隠れしています。
こうしたエピソードや作品内容を聞いて想像できるように、ヴォルテールは一方で観客に人気のある劇作家・作家として成功しながら、他方では言論統制と検閲の下で当局ににらまれる存在でもあったわけです。
王政と貴族社会の中にいながら、それを批判する立場に立っていたことが、彼の生涯を通じた特徴といえます。
イギリス亡命と『哲学書簡』
そんな若いころから辛辣な言葉で貴族や体制を批判していたヴォルテールは、1726年のロアン家とのトラブルによって二度目のバスティーユに収監された後、イギリスへ亡命します。
1720年代後半に数年間滞在したイギリスでは、複数のプロテスタント諸派が共存する宗教状況、議会によって国王の権限が制限される政治制度、ニュートンやロックに代表される学問の発展に触れました。
フランスに戻ったヴォルテールは、このイギリス体験をもとに、宗教的寛容や議会政治、経験と理性を重んじる学問を『哲学書簡』という著作で紹介しています。
世界史の教科書では『哲学書簡』と紹介されることが多いですが、岩波文庫版『哲学書簡』のサブタイトルは「イギリス書簡」とつけられています。イギリス社会を素材にした書簡という性格が表れていますね。
『哲学書簡』ではイギリスを好意的に描く一方で、フランスの絶対王政とカトリック中心の宗教体制を暗に批判していたため、こうした著作は「フランス批判」と受け止められ、発禁処分や焚書の対象にもなりました。
カトリック批判と「寛容」の思想
ヴォルテールが重視したのは「寛容」という考え方です。
信仰そのものを完全に否定するのではなく、どの宗教であれ他者への迫害や強制に結びつくときに問題があると考えました。有名な「カラス事件」では、プロテスタントの家父長ジャン・カラスにかけられた不当な疑いと死刑判決に対して、ヴォルテールがその冤罪を訴え、宗教的偏見と裁判のあり方を厳しく批判しました。
こうした活動は、『寛容論』などの著作にまとめられます。
そこでヴォルテールは、キリスト教の内部だけでなく、ユダヤ教やイスラーム、東洋の宗教などにも目を向けながら、信仰の違いを理由とした迫害をやめるべきだと主張しました。信教の自由や言論の自由、法に基づく政治の必要性を訴えた姿は、フランス啓蒙思想を代表するイメージとなっていきます。
フリードリヒ2世との交流
ヴォルテールはフランス国内だけでなく、プロイセン王フリードリヒ2世(フリードリヒ大王)とも深い交流を持ちました。
フリードリヒ2世は王太子時代からヴォルテールの著作を愛読し、自らフランス語で手紙を書いて議論を求めています。のちに『反マキァヴェリ論』と呼ばれる君主論の草稿をヴォルテールに送り、出版の助言を求めたこともありました。
フリードリヒ2世はヴォルテールと文通や対面で交流を続ける仲で、のちに「啓蒙専制君主」の代表とみなされるようになりますが、ヴォルテールの啓蒙思想が彼の自己イメージや政策に一定の影響を与えたと考えられています。
1750年には彼の招きでヴォルテールがポツダム郊外のサンスーシ宮殿に迎えられ、約2年半にわたって王の側近として過ごします。
しかし、二人の関係は最後まで順調だったわけではありません。
プロイセン滞在中、ヴォルテールは宮廷内の学者たちとの対立や金銭をめぐるトラブルも抱え、しだいにフリードリヒ2世との関係も冷え込んでいきます。数年でプロイセンを去ることになりますが、「啓蒙思想家と啓蒙専制君主が直接向き合った短い時間」として、その交流はよく語られます。
フランス革命とのつながりと評価
ヴォルテールはフランス革命より少し前の1778年に亡くなりますが、宗教的寛容、言論の自由、法に基づく政治を求める姿勢は、18世紀後半の知識人や市民層に広く読まれました。
その影響は、絶対王政と教会の特権に対する批判意識を高め、フランス革命で掲げられる自由や市民の権利の考え方にもつながっていったと考えられます。
革命期にはヴォルテールの遺骸がパリのパンテオン霊廟に移され、フランスの偉人たちが眠る場所に啓蒙の時代を受け継ぐ象徴として扱われました。
同時に、ヴォルテールは完全な民主主義を理想としたわけではなく、啓蒙された王や指導者が法と理性に基づいて統治する体制を現実的な選択肢と見ていました。その意味で、彼の思想はフランス革命のすべてを予告していたわけではありません。
それでも、宗教と王権を理性で検証しようとした姿勢は、「啓蒙の時代」を象徴するものとして、今も世界史のなかで重要な位置を占めています。