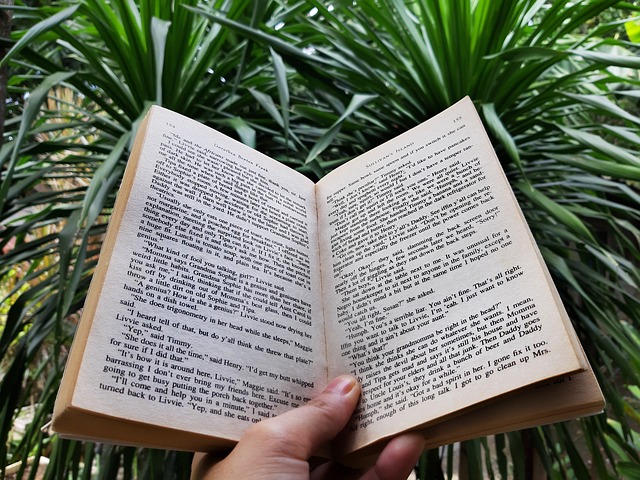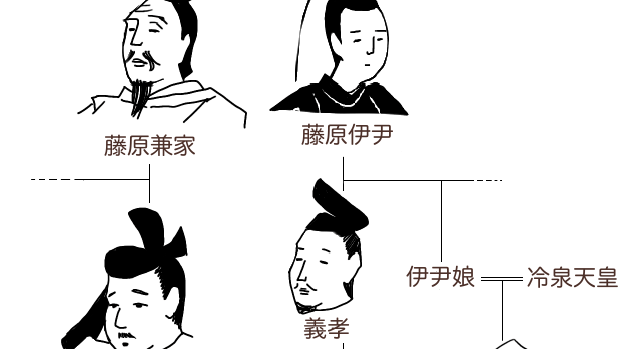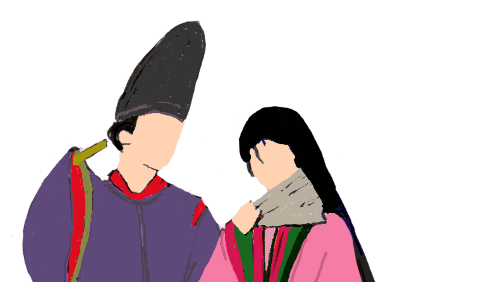平安時代の年中行事と現代の年中行事の起源

これまでのブログでは歴史の流れに沿って出来事の背景を調べたり時には人物を紹介したりしてきましたが、今回は趣向を変えて『平安時代の年中行事』がテーマです。
何かを調べている時に行事の名前は分かっても「いつ頃の時期にどんな目的でどんなことをしていたのか」が分からなければ先に進めない事もあると思うので、覚え書き程度ではありますが、紹介していきます。
年中行事の始まり
平安時代前期に始まった延喜式※から歳時ごとの行事を抜き出し記したものを年中行事記と呼ばれています。この書には、宮中の行事に加えて民間の風習についてしるされており、年中行事と言えば宮中・民間の区別がない季節ごとの営みを表すものとなっています。
※延喜式とは、律令制の時代に宮中での儀式をまとめた書物の事。
中世には年中行事とその習わしのみならず、四季折々の風物なども盛り込んで、中国の書物に倣って歳時記と称されることになりました。特に連歌の世界で歳時記は重視され、江戸時代の俳諧連歌の流行とともにあまたの歳時記が生まれました。
そして、これらが民間に広く受け入れられたことから、年中行事は日本の季節感のみならず美意識や生活感情をも伺い知ることのできるものとなっています。伝統の年中行事は、その行事の内容はもとより、時代背景による営みの移り変わりなども知ることで、はじめてその本質が理解できます。
平安時代の年中行事一覧
| 月 | 行事名 | 内容 |
|---|---|---|
| 正月 | 朝賀 | 元旦に天皇が大極殿に出御する行事。 |
| 元日節会(がんじつせちえ) | 元日の宴会の事。 例えば 七曜御暦奏:しちようごりゃくのそう・中務省が陰陽寮に命じて奉ったもの。 一種の天体暦で現在の曜日とは関係ない 氷様:ひのためし・前年の氷室や氷池の様子からその年の吉凶を占う儀式で宮内省によって奏された 腹赤の奏:はらかのそう・大宰府から腹赤【=マス】を朝廷へ献上、内膳使【=天皇の食事を司る役所】が受けて奏した儀式 などがある | |
| 白馬節会 (あおうませちえ) | 7日の青馬引きの行事。 中国伝来の儀式で元は青みがかった黒馬だったが、時代と共に日本化。 白馬を用いるようになった。元々、春の初めに青い馬を見ると一年の邪鬼を払うという故事に由来。 | |
| 朝覲行幸 (ちょうきんのぎょうこう) | 天皇が上皇や母后の御所へ行幸、年始の挨拶をすること。こちらも唐由来の儀式。 | |
| 二宮大饗 (にぐうのだいきょう) | 群臣が中宮・東宮へ拝賀し、宴を賜る。 | |
| 大臣大饗 (だいじんのだいきょう) | 摂関大臣家の私邸での宴で、藤原冬嗣より伝わる朱器台盤を用いる。 | |
| 叙位 | 大臣以下五位以上の臣下に位階を授ける儀のこと。 | |
| 七草 | 民間の若菜摘の行事が宮廷の歳事に。 | |
| 御斎会 (ごさいえ) | 天皇が大極殿に出御、高僧を集めて金光明最勝王経を講説。 | |
| 卯杖 (うづえ) | 邪鬼払いのため、杖を天皇・東宮に献ずる行事。中国の故事に由来。 | |
| 御薪 (みかまぎ) | 15日に百官が燃料として薪を宮中に献ずる儀のこと。 | |
| 十五日粥 (もちがゆ) | (望粥とも) 小豆入りの粥を作って天皇に献上する。一年中の邪気を祓うとされている。 | |
| 踏歌節会 (とうかのせちえ) | 天皇が年始の祝詞を歌ったり舞ったりする踏歌(足を踏み鳴らしながら歌ったり踊ったりする集団舞踊で大陸から伝来)を見物した後、五位以上の者を招いて宴を行った。日本古来の歌垣(歌舞飲食や豊作の予祝、求婚するための行事)と結合したそう。 | |
| 射礼 (じゃらい) | 天皇臨席のもと建礼門前で六衛府の射手が弓の技を試みた行事。優秀者には賞が賜られた。 | |
| 賭弓 (のりゆみ) | 射礼の翌日にあった弓術競技で、負けた側は勝った側にご馳走した。 | |
| 二月 | 祈年祭 (としごいのまつり) | 一年の五穀豊穣を神に祈る儀式。神祇官で行う。 |
| 列見 (れっけん) | 式部省・兵部省が選んだ六位以下の官人の功過を考査し、叙位すべき者を太政官が検閲する年中行事。 | |
| 初午 (はつうま) | 二月の初午の日に行う稲荷神社の祭礼。711年2月11日に祭神が稲荷山に降りたとされることが由来。 | |
| 春日祭 | 藤原氏の氏神祭。前日に朝廷から神馬(じんめ)を派遣するための勅使(春日使)が立てられていた。 | |
| 三月 | 上巳の祓 (じょうしのはらえ) | 3月の初巳の日、人形に罪を託して水に流す行事で、現在のひな祭りの起源とされています。 |
| 曲水宴 (ごくすいのえん) | 水に盃を浮かべて流し、その流れてくる杯が自分の前を通り過ぎるまでに詩歌を作り読む行事。 | |
| 雛祭 | 三月の祓えと形代としての人形が結合した | |
| 四月 | 旬 (しゅん) | 元は毎月行われていたが、平安中期以降は4月と10月のみ行われるように。 いわゆる旬宴のことで、天皇が臣下に酒を賜り政務を聞く儀の後に宴を行った。 |
| 灌仏会 (かんぶつえ) | 釈迦の誕生を祝う仏教行事で、仏像を灌浴(かんよく)する。 | |
| 賀茂祭 | 4月中の酉の日に行う賀茂神社の祭礼。現在では葵祭として残っている。 | |
| 五月 | 端午節会 | 元は五月は悪月という考えの元で邪鬼払いをする中国の風習が変化して日本でも年中行事として定着。 |
| 六月 | 忌火の御膳 (いみびのごぜん) | 不浄の火を改めて新しい火で炊いたご飯を神様に献上する行事。 |
| 月次神今食祭(つきなみじんこんじきさい) | 6月と11月の11日に神祇官で行われた儀で、国家の安泰と天皇の長寿を祈る。 | |
| 祇園会 (ぎおんえ) | 疫病退散のために6月15日前後に行われる夏祭りのこと。祇園祭として現存。 | |
| 六月祓 | 罪と穢れを取り除くために行われる祓。 | |
| 七月 | 七夕乞巧奠 (たなばたきっこうてん) | 漢代の織女(しょくじょ)と牽牛(けんぎゅう)の伝説と唐代の願掛けが融合したものが伝わった。 織女の機織りやお裁縫が上達するよう祈りが込められた。 平安時代には相撲や宴が開かれるようになっている。 |
| 于蘭盆会 | インドから伝わった儀式で、祖霊を祀り僧侶を供養する。 | |
| 相撲節会 (すまいせちえ) | 元々は7月7日に行われていたが、平安中期以降は7月後半に行われるように。 | |
| 八月 | 定考 (こうじょう) | 列見・擬階奏(ぎかいのそう・令制下級官人の位階授与の手続きのうちの一つで4月に式が行われた)で選ばれた人々の官職を朝廷で決定させる。 |
| 九月 | 重陽宴 | 菊花の宴のこと。 |
| 伊勢奉幣 (いせほうへい) | 幣帛(へいはく・神前の供物のこと)を伊勢神宮に献ずる行事。 | |
| 月見 | 月を愛でて収穫を喜ぶ宴で、詩歌管弦を行った。 | |
| 十月 | 更衣 (ころもがえ) | 装束や調度類を取り換える行事。 |
| 残菊宴 | 陰暦10月5日に残菊を観賞。 | |
| 亥子餅 (いのこもち) | 10月亥の日に餅を食べることで年中の病を避けようとした。 | |
| 十一月 | 新嘗祭 (にいなめさい) | 天皇が新穀を天神地祇(てんじんちぎ)に献上、自らも食す行事。その年の収穫に感謝する。 |
| 豊明節会 (とよのあかりせちえ) | 新嘗祭翌日の宴で、※五節舞(ごせちのまい)が行われる。 ※現在でも行われていてYOUTUBEで見つけたので下に貼っときます。 | |
| 十二月 | 御仏名 (ご・おぶつみょう) | 高僧に諸仏の名を唱えさせ、罪の消滅を祈る行事。 |
| 追儺 (ついな) | 晦日の夜、禁中にて悪鬼を祓う儀式の事。 | |
| 御魂祭 (みたまさい) | 七月の盆と似た死者の霊を祀る行事。 | |
| 荷前 (のさき) | 諸国から貢物として届けられた初穂を年末に幣帛として天皇の稜や外戚等の墓に献ずる儀式。 |
みんなも知ってる年中行事の起源
上記の一覧でも七草や端午の節句などのお馴染みの年中行事がありました。
そこで、みんなも知っている年中行事をピックアップして、起源などを紹介していきます。
一月の年中行事 左儀杖(さぎちょう)【どんと焼き】
門松やしめ飾りを焼くことによって炎と共に見送る意味があるとされ、1月15日に燃やす習慣があります。地方によって、【どんと焼き】【どんど】【どんどん】など様々な呼び名があり、出雲地方の風習が発祥であろうかと思われています。
起源は、平安時代の三毬杖(さぎちょう)【3本の毬杖を立てて燃やした】ところからの名称とされています。毬杖というのは槌型の杖で、古くは正月に木製の玉を打って遊ぶ『ホッケー』のような競技で、南九州では正月の風俗として残っているそうです。
また、左利きの事を左ぎっちょと呼ぶのも関係があるとも言われています。
二月の年中行事 追儺【節分・豆まき】
節分は、【季節の変わり目】と言う意味で、もとは立春・立夏・立秋・立冬のそれぞれの前日をさしていましたが、現在では主に立春の前日を節分と言っています。
平安時代の節分は、これと言って特別な行事はなかったようですが、方違をした記録が残っており、節分は【厄を祓うべき日】と考えられていました。
中国では、人に厄をもたらす鬼を追って来るべき春に福を求める風習がありました。
【桃の弓に棘〔よもぎ〕の矢】を射て、五穀・小豆、ときに小石をも撒いたされています。これが現代の日本で行われている豆まきの起源だと言われています。
春を迎えるにあたり鬼を追う行事として、日本では宮中の【追儺】の行事として大みそかに行われていました。これには、新年を迎える準備の意味がありましたが、陰暦の正月は立春ともにが近いため、室町時代の頃から春を迎える立春の前日が節分の行事となりました。
節分と言えば、年齢の数だけ豆を食べるのがありますが、この起源には『古事記』などの日本の神話で身の不浄や罪悪を祓うために身に着けていた衣服を捨てるという風俗が、古くから日本にあったそうです。
これを節分の厄払いの風俗と結びついて、節分の日に自分の衣服を街路に棄てることで厄を祓う事がありました。こうして捨てた衣服が乞食者への施しとなることから、ついには自分の年齢の数の銭を包んで落とすことにもなりました。
1600年ころの後水尾天皇が歳の数だけ豆と鳥目〔ちょうもく=銭〕とを包んだものを厄払いのために撫でたことから、これが年齢の数だけ豆を食べるという風俗につながったのではないかと考えられています。
三月の年中行事 ひな祭り・上巳の節句
3月3日は、上巳の節句と呼ばれ、この日は古くから一年のうちで最も陰の極まる悪い日であると信じられていました。紀元前の中国では、この不吉な日にケガレを洗い流す意味を込めて水辺に出て口をすすぎ手を洗う風習がありました。
この風習がいつしか、雅な遊びに一日過ごすと言うものに変わっていきました。
日本では、7世紀ころからワラを人のかたちにしたものでからだを撫でるようにして自分の悪いものを移し、水に流してケガレを捨てる風習がありました。これを「撫で物」や「形代〔かたしろ〕」と呼び、後の雛人形の起源となっていきました。
14世紀になると、3月3日に人形を贈る風習が始まり、その人形を枕元に置いて眠ると身にふりかかるケガレを人形が代わりにとってくれると考えられるようになりました。その翌朝に、その人形を寺に持っていきケガレを取り除くようになりました。
この習慣は、上巳の風習が影響したのだと思われています。
五月の年中行事 端午の節句【こどもの日】
端午の節句の端午とは【初め】と言う意味を持っています。
【午】は、十二支による【午(うま)】で、日本でっは午年に当てられることが多く、中国では月日にも十二支が当てはめられます。もとは、毎月初めの午の日を【端午】と呼ばれていましたが、五月が【午の月】なので、牛の月の端午※が重要視されるようになりました。
※五月の最初の午の日
中国では、奇数月が縁起が悪いとされていたので、端午の節句は厄除けの意味合いが強かったのですが、日本ではむしろ奇数は吉とされてたので、端午の節句はお祭り的な年中行事となりました。
七月の年中行事 七夕
7月7日(一部地域では8月7日)の七夕ですが、現代の日本では、織姫・彦星の伝説や短冊に願い事を書いて吊るした経験はあると思います。
7月7日に行事が行われるようになったのは、古代中国の魔よけの風習からですが、いつからか牽牛と織姫伝説に結びつくようになりました。織姫は、機織りを司るとされていて、7月7日は夜に機織りの上達や裁縫や手芸一般や詩歌など幅広い芸事の上達を祈る行事と変わりました。
現在の、短冊にお願い事を書くという風習は、そこから来たのではないかとされています。
【たなばた】の呼び名は、日本での織姫が【棚機つ女(たなばたつめ)】と呼ばれていたことから【七夕】となったようです。
当時は7月だった年中行事のお盆
正月と並んで日本の二大年中行事の【お盆】は、【盂蘭盆会(うらぼんえ)】が略された名前だと言われています。
盂蘭盆とは、ウランバナに由来されると言われています。これは【倒懸=逆さに吊るされる】と解釈され、餓鬼の道に逆さに落ちて苦しむといわれており、仏陀の教えしたがい7月15日に僧侶に供養することによって、七世の父祖と共に母の霊を救ったと言われる故事が起源とされています。
日本では、7世紀の斉明天皇の頃から始まったとされ、平安時代には貴族の年中行事として行われていました。この時は、故事の通りに僧侶に対して食物等を供えていましたが、現代ではお墓(死者)に対して供えるというものに変わっています。
これは、室町時代に、餓鬼道に落ちた者を救済する供養である【施餓鬼会(せがきえ)】からきていると考えられています。
また、お盆の期間については、旧暦と新暦の違いで7月15日と8月15日になっていると言う事でした。しかし、関東では新暦に切り替わった後も同じ日付で行っている所もあるそうです。
十一月の年中行事 七五三
11月は、子供たちの健やかな成長を祈る行事として七五三のお宮参りの風習が定着しています。現代では、15日が七五三の式日としていますが、これは室町時代の武家の間で定まった日取りです。
年中行事の元は、やはり平安時代の公家社会ですが、起源は定かではありませんが、「髪置き」・「深曽木」・「着袴」・「帯解き」の行事が合わさって現在の行事につながっているようです。
髪置き
子供が3歳になるころの儀式で、平安時代の中頃から行われていたとされています。
赤子が誕生すると、産毛を剃り落とし、その後も髪を伸ばさずいたようですが、【髪置き】を境に伸ばし始めます。鎌倉時代になると、子供を碁盤に座らせ髪の毛にさまざまな縁起物を結びつけて、子どもの健康と成長とを願うという儀式になっていました。
着袴
着袴は子どもが初めて袴を着ける儀式で、ちゃっこと読みます。
当初、年齢は、3歳から8歳と決まっていなかったのですが、後に5歳から7歳と定められていきました。
儀式の席では、介添えのものが子どもの前に袴を捌いて置き、親が子どもを支えて両足一度に袴の中に踏み込ませ、腰を結びます。さらに二人の大人が装束を着付け、男児には父親、女児には母親が中心となって装束を着付けてやるのが普通でした。
深曽木(ふかそぎ)
子供の髪の毛が胸元まで伸びたころに髪を切りそろえる儀式で、【深曽木】と呼ばれています。髪の毛の長さが儀式の目安となるために、当初、年齢や日取りは一定しませんでしたが、男子は5歳・女子は4歳と室町時代に行うようになり、11月や12月の吉日が選ばれるようになりました。
帯解き
着袴のときに子どもが着ている小袖は、袖に振りがあり、また両襟の先に小紐がついていてそれを背中で結んで留める形式のものでした。しかし、しばらく経つと、この小袖の襟先の紐を取り去って、大人と同じように腰に帯を締めるようになります。
室町時代の末ごろからは、これも子どもの成長儀礼のひとつとして、「帯解き」・「帯直し」・「紐落とし」・「紐直し」などの名で呼ばれました。
以上は、もともと別の儀式でしたが、着袴と深曽木の時期は近いことや江戸時代になるとすべて同時にやることが多かったようです。現在でも皇族殿下方は、親王殿下は「半尻」、内親王殿下は「細長」の御装束で、江戸時代初期からの伝統にのっとった「着袴の儀」をお挙げになります。
少々長くなりましたが、簡単に年中行事について書いていきました。
平安時代の行事として紹介していますが、その始まりは本格的な律令国家になろうとしていた前後の時期から始まったものが多数です。また、唐から伝わった行事が日本の元々の信仰や行事と融合したものもあり、和漢折衷?が本格的に進んでいたのだろうことが想像できますね。
参考文献:朝日百科 日本の歴史3 -古代から中世へ- 2005年出版 朝日新聞社より