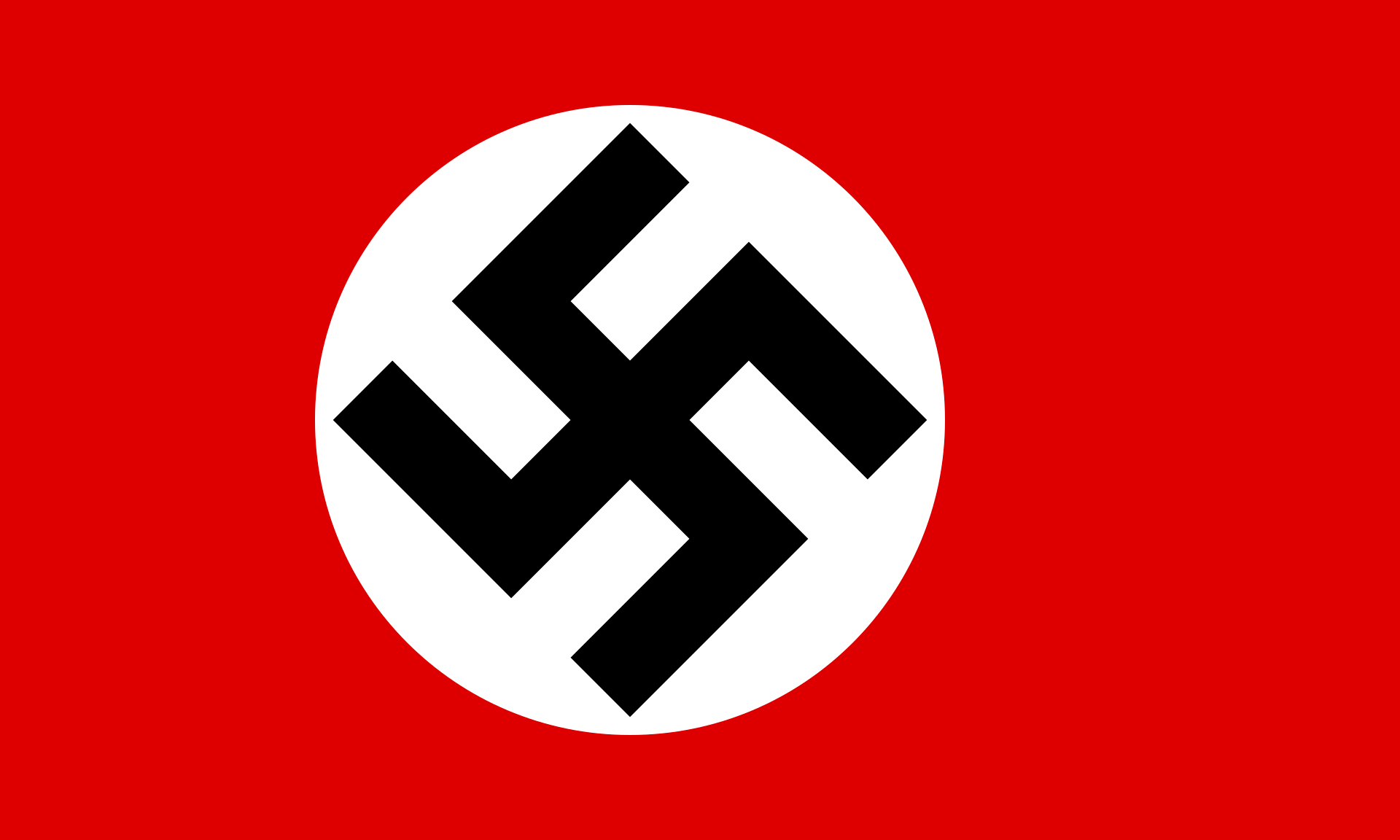歴史問題と第二次大戦の戦後処理

私が歴史を改めて勉強をしようと思ったのは、時事問題を深く掘り下げていきたかったのが理由でした。今回、似たような主旨でPRESIDENTと言う雑誌の『儲かる「歴史学」』という記事が載っていました。現代史にもつながる内容が書かれていましたので、ちょっと紹介していきたいと思います。
今回は終戦記念日という事で戦争絡みの話を。世界史(特に中国史)も含まれます。安倍首相が談話を発表しましたが、何故ここまでこじれたか?も分かり易かったので『儲かる「歴史学」』をまとめつつ、その背景もみてみます。
日中の歴史的背景
日中関係の現在を知るには日中の近世史(特に後半)を知る必要が出てきますので、日本の江戸時代と中国の明・清の時代の政府の方針を少し探っていきましょう。
- 日本…地方の発展を歓迎 ⇒ 各藩で学校の整備に力を入れ、経済も発達
- 中国(明・清)…地方の発達を脅威とし、あえて指導せず
このような政府の方針になった背景にも様々な要因が絡んでくるとは思います。中国がそれまでの伝統(中央による地方のコントロールが弱かった)多民族国家であることなどが挙げられそうです。国内で有事が起こった際に周辺国や周辺民族につけ入る隙を与えたくなかったからかもしれません。
更に、近代化に失敗したのにも理由があります。清は隆盛を極め、人口は18世紀末に3億人を突破。その後も4億人以上に増え続けますが、同時に人口過剰による自然破壊からの災害が多発。この混乱により内乱が起こります。ちょうど同時期に西洋列強の侵略があり、対抗するための近代化を目指しますが足元の不安定な清王朝ではその目的を達成することはできませんでした。
私自身が中国史も大好きなので、ヨーロッパに好き勝手された被害者的な視点だけだと正直モヤモヤします。そんなに弱い国だったのか?という意味で。そんな個人的な視点がちょっぴり入っているかもしれません。一応調べた上で、↑の説を紹介していますが。
もう一方の日本はどうかと言いますと。一般的に地方が強くなると中央政府のコントロールが効きにくくなると言われますが、その対策として徳川幕府では大名の家族を人質とする参勤交代を制度として取り入れています。これが地方の発達を歓迎する余裕となったようです。この地方の発達は日本の近代化に大きく貢献したと思われます。
なお、鎖国と言われる時代の中、大名の一部には参勤交代の負担を和らげるべく琉球(を介して中国)やロシアとの貿易をするような藩も実はあったそうです。薩摩はその代表で、遠い場所から参勤交代行っていても財政的には他藩に比較すると余裕があったと言われます。
また、江戸時代に儒学(特に朱子学)を一つの学問とし、立身出世のための手段(の一つ)にもなったことも大きく関係しています。朱子学は江戸時代の身分秩序の考え方や封建支配をするための思想と一致するために採用されています。言い方は荒っぽいですが、徳川を正当化するイデオロギー(考え方)のようなものを全国的に広げて逆らえないようにしようという意図があったと思われますし、実際に長らくそれは上手く機能していました。このイデオロギーの浸透も地方の発展を歓迎する要因になったことでしょう。
皮肉にも朱子学がかなり研究されるようになった江戸末期には主君である将軍を絶対視するよりも天皇を・・・という思想(=尊王攘夷)となり、明治維新の原動力となりますが。
とにかく、この差が第二次世界大戦後にも尾を引きます。中国は1978年の改革開放路線を経て本格的な近代化が始まり、近年になってから国産産業が発達。現在、GDPは日中で逆転するまでになりました。
第二次世界大戦の戦後処理

よく比較されるのはドイツの戦争責任ですが、「責められる」ということは相手あってのこと。違いは日本とドイツの関係各国のパワーバランスにあると言われています。
ドイツの戦後処理
まず、ドイツ。ドイツの近隣諸国は第2次世界大戦中に主役クラスで戦った発言力の強い国が多いことが挙げられます。さらに戦後は1949年までの占領期を経た後、領地を分断されたりと非常に弱い立場にありましたし、冷戦時代の最前線にもなりました。そんな状況下で1945年設立の国際連合や1949年にできたNATO(北大西洋条約機構)に参加できないのは致命的でした。周辺国との和解が不可欠だったそうです。譲歩せざるを得ない状況だったわけです。
第二次大戦の日本の戦後処理
日本はメインとなる対戦国はアメリカと中国。戦後1952年までアメリカを主軸とする連合国の占領下に置かれています。
その間に隣国であった事と言えば、1946年からの国共内戦(中国・国民党 VS 共産党)、1950年~の朝鮮戦争。国共内戦は1949年に今のような形で落ち着きます。朝鮮戦争は、西と東の代理戦争でもあります。どちらも民主主義と社会主義の対立とも絡んでくる戦いです。
恐らく、これらの混乱から日本の戦後処理は遅れました。52年の台湾との日華平和条約、65年の日韓基本条約、72年の日中共同声明と終戦から時間が経過しています。日本はその時間の経過と共に経済含めた復興を果たしています。中国はこの時期ソ連と対立関係にもあったことからスムーズに関係を改善する必要がありましたし、韓国では61年にクーデターで成立した朴正煕(パク・チョンヒ)政権が不安定だったことが日本にとって好材料になりました。
こういった事情から日本は戦後処理の際に優位な立場で臨むことでき、そんな経緯から中韓共に潜在的な不満があったのではないか?としています。加えて最近怪しいとは言え、両国ともにかなりのスピードで経済発展してきました。パワーバランスが当時と変化したことでその不満が「歴史問題」として噴出しているのではないか、というわけです。
他にも様々な要因があるでしょうが、パワーバランスの説が割としっくりきますね。上手く言えませんが、特に中国の場合は他国に対抗しようとした時期にちょうど足元がぐらつき、上手く乗り切ることが出来なかったことが現在までも尾を引いているような気がします。
ここ最近の中国はその経済発展に急ブレーキがかかっている状況ですので、場合によっては多少のトーンダウンはあり得るかもしれませんね。どちらにしても今後の力関係が物を言いそうです。