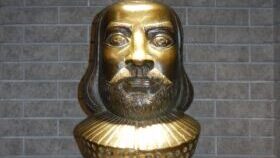五か条の御誓文とは?どんな内容が書かれていたのか詳しく解説!
幕末の混乱を経て1867年には徳川慶喜が政権を朝廷に返上する大政奉還が行われた後、天皇の下で新たな政府が出来上がります。
最初は徳川慶喜中心の政府になりかけたのですが、討幕しようと動いていた者達にとっては面白いはずもなく、徳川家を潰そうと動き王政復古の大号令を発布しました。これにより新政府を作ることを全国に宣言しますが、こちらもまた慶喜により骨抜きに。結果起こったのが戊辰戦争(1868年1月-1869年)です。
こうした事実の羅列だけでも日本の混乱っぷりが分かるかと思います。そんな感じで日本が混沌とした中、1868年3月14日、江戸城総攻撃予定の前日に公布されたのが五か条の御誓文です。
今回は、その五か条の御誓文について公布された目的や内容などについて簡単にまとめていきます。
五か条の御誓文の目的
新政府が起こって新しい時代に入ろうかという頃、日本国内では内乱の戊辰戦争が始まります。戦争中には一揆や打ちこわしの頻度が最高潮に達するほど治安が悪化。情勢を落ち着かせるためにも先の見通しを見せる必要がありました。
そこで新政府が「日本の今後の基本方針を示そう」としたのが五か条の御誓文。天皇を中心として行う新しい政治の基本方針を明らかにして希望を持たせようとしたのです。
誰が作ったの?
五か条の御誓文は日本の内乱・戊辰戦争が始まったのと同じ月に越前藩出身の由利公正(ゆりきみまさ)が原案を起草、土佐藩出身の福岡孝弟(ふくおかたかちか)が修正、長州藩出身の木戸孝允が加筆した後に公卿で参与の東久世通禧(ひがしくぜみちとみ)を通して議定の岩倉具視に提出されました。
※参与も議定も王政復古の大号令で新たに設置された職の一つで王政復古の大号令の記事に書かれています。
由利公正も福岡孝弟も木戸孝允も参与です。
五か条の御誓文の内容は?
上記のような経緯で生まれた五か条の御誓文は「明治天皇が天地の神々に誓約する」という形で示されました(原案では天皇に対して諸大名が誓約という形で行おうとしていたそうです)。
具体的にどんな内容だったのかを見てみましょう。
- 広ク会議ヲを興シ万機公論ニ決スヘシ
- 上下心ヲ一ニして盛ニ経綸ヲ行フヘシ
- 官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス
- 旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ
- 智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ
広ク会議ヲを興シ万機公論ニ決スヘシ
日本中から人を集めて会議を開き、議論を交わしたうえで公正な意見をもって政治的な決定を行うことを目指しました。
江戸時代には限られた士族たちの中でも、さらに限られた者たちによる会議で政治が進められていました。
後々の国会開設で見られる形態の政治運営法ですね。
上下心ヲ一ニして盛ニ経綸ヲ行フヘシ
身分が上の者も下の者も心を一つにして経済や財政を安定させて国を治めようという意味です。
最初の原案だと身分など全く関係なしでというような内容でしたので、若干、身分格差を暗に認めるような内容に変化しています。
官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス
公家・武家が一体となるだけでなく庶民も含めて誰もが職責を果たし、志を全うできる社会を目指すことが書かれています。
第三条に「官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメンコトヲ要ス」とあることは、指導層のみならず国民一般の教育組織を、構想企画する政策に連なるものであったといえよう。
文部科学省『明治新政府の文教政策』明治維新と教育の基本方針より
上記の文科省から引用した文章は教育理念に関する「職責」について書いていますが、教育場面に限らず其々の職務に責任を持ちましょうということでしょう。
これは近代化のための心構えのようにも見えますね。後の殖産興業にもつながる話かと思います。
旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ
旧来の悪習を打破して国際法(=天地の公道)によって開国和親を図りましょう、という意味。
さんざん攘夷してきましたし、近代化には和親が必要不可欠です。
智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ
日本の伝統も大切にしつつ、世界の幅広い知識も積極的に取り入れて天皇を中心に国を発展させようといった内容が書かれています。
第4条の悪習に関する文章と合わせて「日本の悪いところは捨てなきゃダメだけど良いところは残していこうね」というところでしょうか。
そして最後に
我國未曾有ノ變革ヲ爲ントシ、朕󠄂躬ヲ以テ衆󠄁ニ先ンシ、天地神󠄀明󠄁ニ誓ヒ、大ニ斯國是ヲ定メ、萬民保全󠄁ノ道󠄁ヲ立ントス。衆󠄁亦此旨趣ニ基キ協心努力セヨ。
明治天皇が国民に向けて大変革を行うにあたる決意をもとに国政の基本方針を定め、神々に誓ったので、皆さんも協力・努力してくださいという締めくくりの言葉を述べられました。
五か条の御誓文と五榜の掲示の違いとは?
最後になりますが、五か条の御誓文と同じような時期に似たような名前で間違いやすい歴史用語『五榜の掲示』があります。
その違いにだけ触れていきましょう。
| 五か条の御誓文 | 五榜の掲示 | |
| 誰が誰に、どのように? | 天皇が神々に宣誓する形で | 政府が民衆に向けて |
| 内容 | 新しい政治の基本方針 | ・親兄弟、友人を敬って、殺人・放火などをしない ・一揆を起こさないなどの禁止令 |
| 出した日 | 1868年3月14日 | 五か条の御誓文を出した翌日 |
ということで、内容がだいぶ違います。五榜の掲示の中には「キリスト教を信仰しない」という内容が含まれていたため、1873年にはすべて撤回されることになっています。